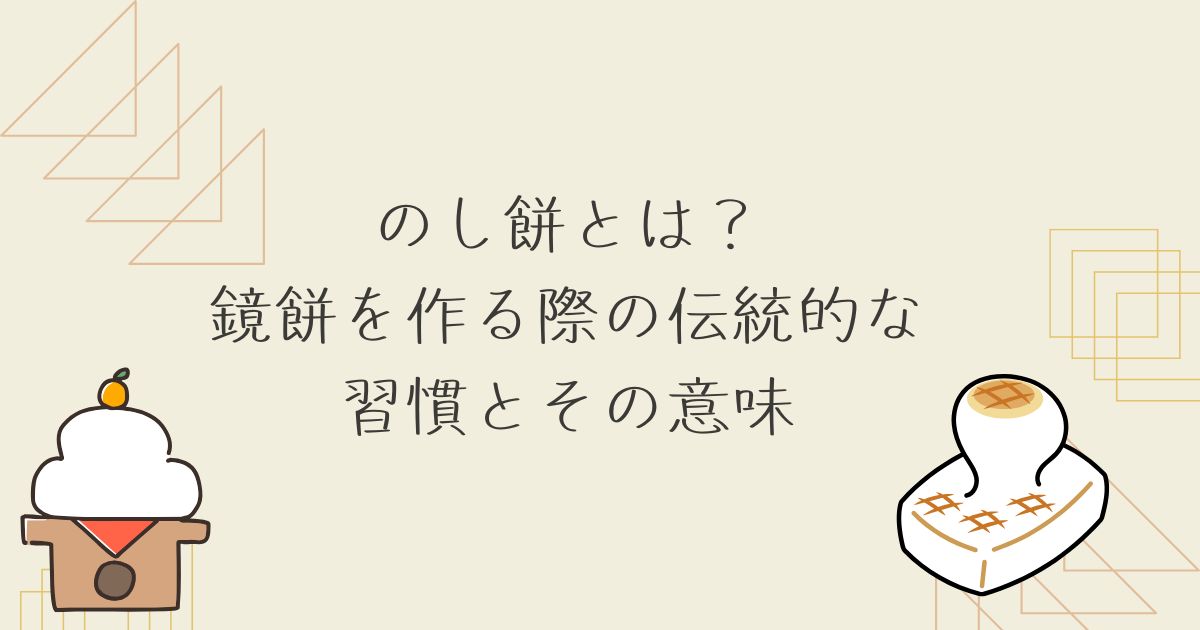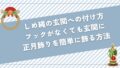日本における年末に欠かせない行事がお餅つきです。
この行事は歳神様を迎える重要な儀式とされ、全国各地で今も盛んに行われています。
この時に作られたお餅は、まずは神様専用の鏡餅として設けられ、次に人々が食べるために分けられます。
この分けた後のお餅を平たく伸ばしたものが、のし餅です。
「のし」の意味は「伸ばす」や「広げる」といった行動を指し、名前の通りの働きをしています。
この平らに伸ばされた「のし餅」は、少し時間を置いてから固まり、食べやすいサイズに切り分けられます。
一方、こののし餅の習慣は特に東日本で見られることが多いです。
西日本では、ついたお餅をそのまま個別に丸めて、丸餅を作ることが一般的です。
のし餅と切り餅、同じものなの?その違いは?
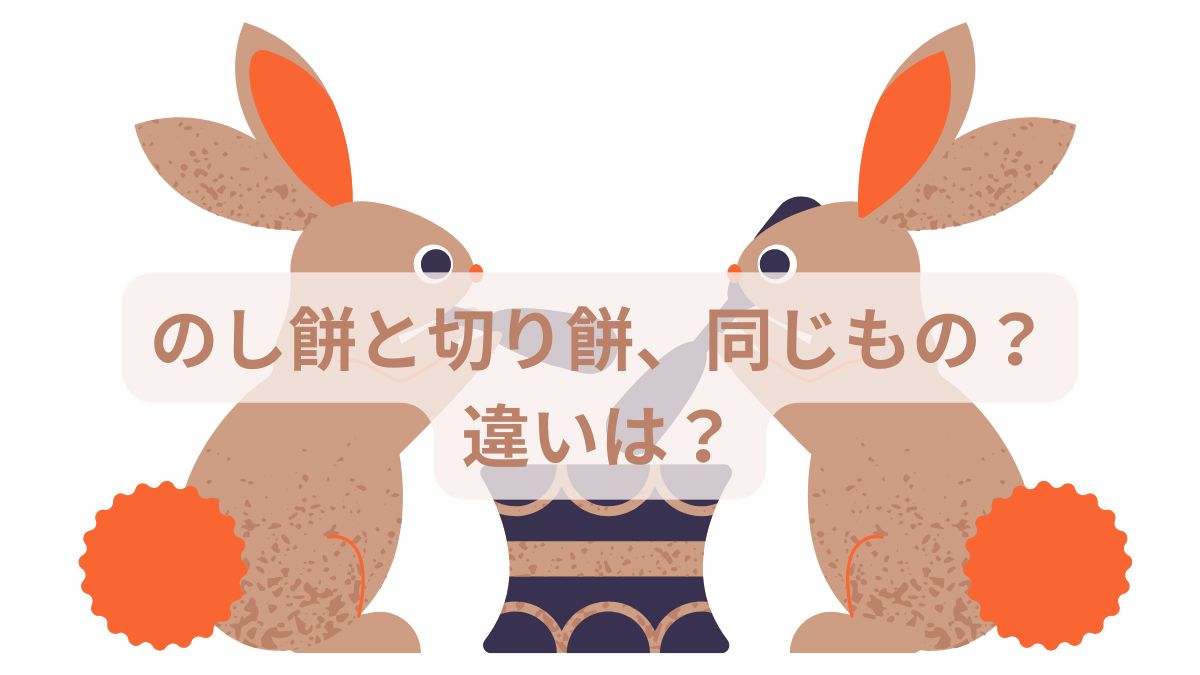
先程のし餅について説明しましたが、それが固まった後に切り分けられる点に触れました。
この手順で作られる四角形のお餅が切り餅と呼ばれています。この名前は、文字通り切り分けられた餅を指します。
そのため、のし餅と切り餅の間には、成分や素材に違いはありません。
切り餅は単にのし餅を切り分けたものです。
のし餅を切り餅にする理由とは?そのままでは食べにくいから!
のし餅は通常、餅つきの際に1升(約1.5kg)のもち米から作られます。家庭用の小型餅つき機では1合や2合で作ることも可能ですが、伝統的な臼と杵を使用する場合は、大量生産に適しています。
日常では、お米を炊く量が3合や5合のため、1升のもち米がどれほどの量か想像できるでしょう。もち米1合は約150gなので、1升だと1.5kgです。
このもち米から作られるのし餅は約1.5〜2cmの厚さに伸ばされます。この大きな板状の餅をそのまま食べるのは非現実的です。
そこで、食べやすいように切り餅として小分けにされます。切り餅は硬くなりがちなので、切る際は包丁を温めてから行うと良いでしょう。水分を避けるために、切る前に包丁を拭くのがおすすめです。
切り餅は保存しやすく、また食べ方も多様です。鍋料理やお雑煮に入れる、焼いて醤油や味噌で味付けする、甘味が好みの場合はあんこや黒蜜を添えても楽しめます。
しかし、お餅は高カロリーで糖質も多いので、食べ過ぎには注意が必要です。一般的な切り餅一個のカロリーは約120kcal、糖質量は約25gとなっています。
いつでも手軽に楽しめる!のし餅の通販サービスが充実
のし餅は今や通販で簡単に購入できるようになりました。
年末に人気が集中するものの、現在では一年を通してさまざまな通販サイトで扱われています。Amazonや楽天など大手通販サイトで「のし餅」を検索すると、数多くの商品がヒットし、その多様性には目を見張るものがあります。
商品のバリエーションも豊富で、1升だけでなく様々なサイズや形状があります。板状のもの、切れ目が入っているもの、あらかじめ切り餅として加工されているものなど、選択肢は多岐にわたります。
さらに、ヨモギ、キビ、大豆、黒大豆、青海苔などを練り込んだ風味豊かなものも見受けられます。
このように、個々の好みに合わせて選べる豊富な種類があるのは、とても便利で楽しいことです。
まとめ
私の祖父母宅でも、叔父叔母、従弟たちによって毎年年末にはお餅つきが行われています。
叔母が蒸し上がったもち米を準備し、叔父と従弟が中心となって臼と杵で餅をついています。最近は電気の餅つき機も併用しています。
まずは新しい年を迎える準備として、お鏡様(鏡餅)を作ります。ただし、搗きたての餅は形が定まりにくいため、鏡餅の各段を形成してから少し硬くなるまで待ち、その後で重ねて床の間に飾りつけるのです。
鏡餅を作った後は、食用の餅を作ります。私の家は中部地方に位置しており、東日本で一般的なのし餅を作っています。
買った餅も美味しですが、やはり臼と杵で自宅で作るのし餅は一味ちがいますね。